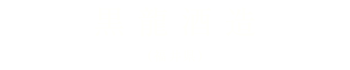01
Mar
2016
黒龍
庶民に親しまれた通い徳利
一升瓶が普及する明治後期以前に、庶民の間でお酒を入れる容器として親しまれていたのが「通い徳利」と呼ばれる陶磁製の徳利です。
当時は、酒屋から貸し出された通い徳利を容器とし、注いだ量に見合った金額を支払う量り売りのスタイルが一般的でした。貸し出された徳利の側面には、店の屋号をはじめ、住所やお酒の銘柄が書かれ、店の広告としても一役買っていたようです。
弊蔵母屋の倉庫を覗くと、屋号の石田屋と書かれた通い徳利や、店先でのお酒の販売、清酒の運搬や貯蔵用の容器に使われた「瀬戸樽」が、今も大切に保管されていました。
残された道具を眺めながら、当時の黒龍酒造の営みを想像してみると、埃をかぶった徳利や樽のひとつひとつが、まるで宝もののように思えてくるから不思議です。
写真右:蔵の棚に残された通い徳利 写真左:無地の瀬戸樽

黒龍 - 2016.03.01